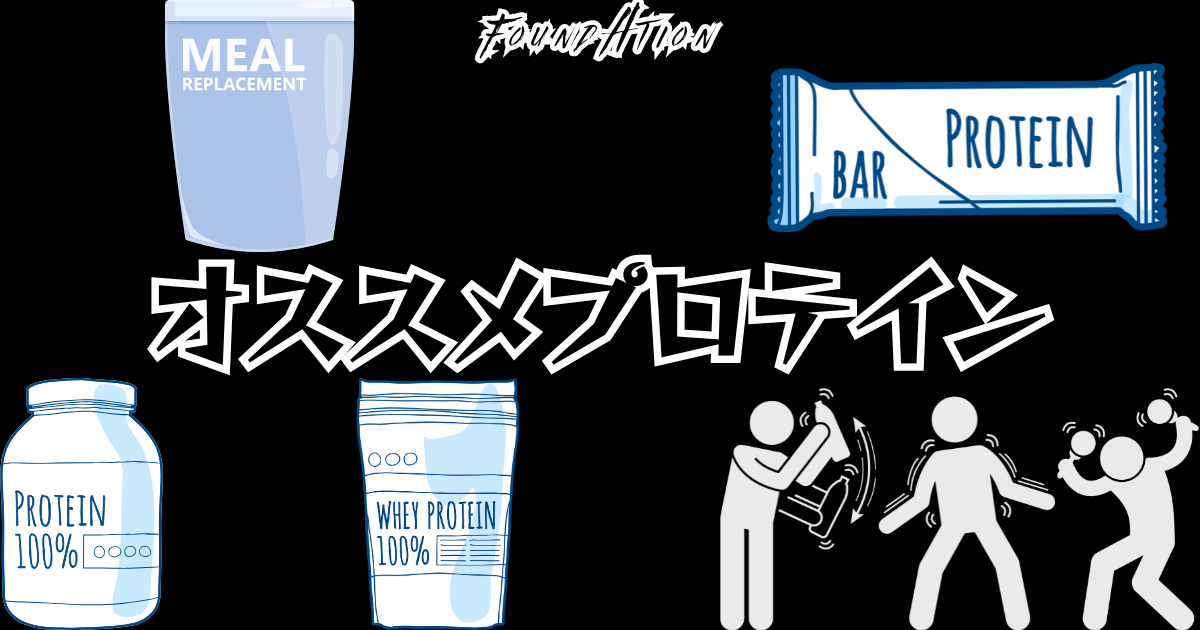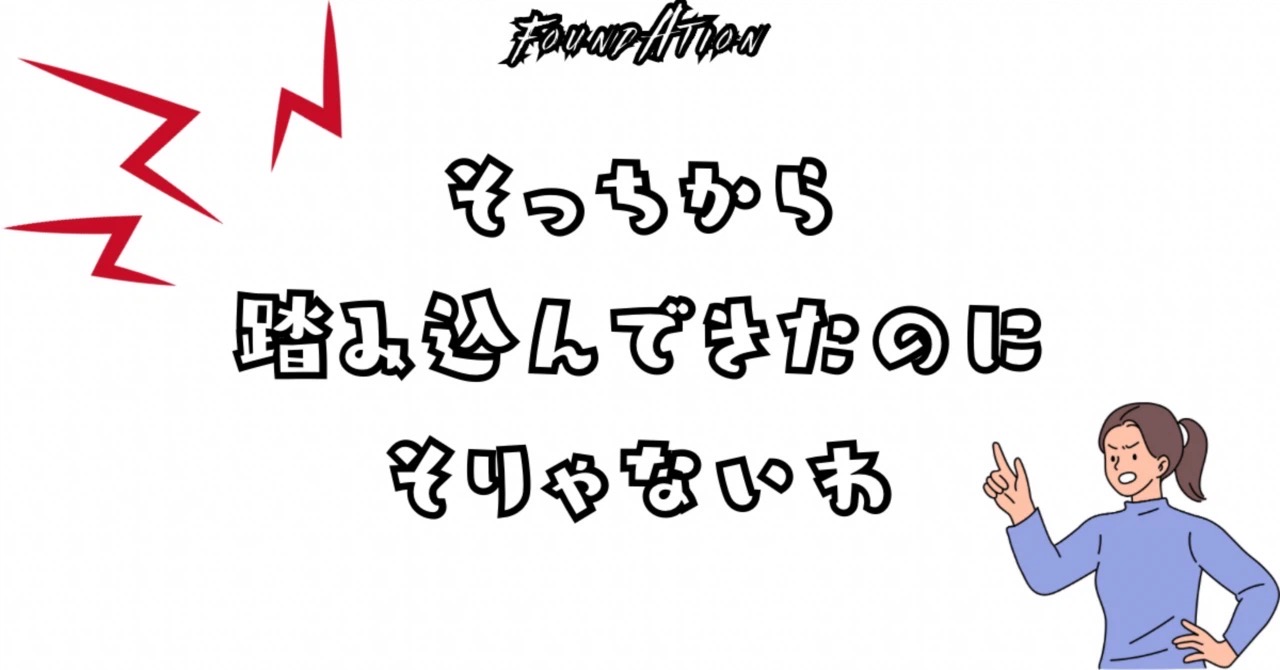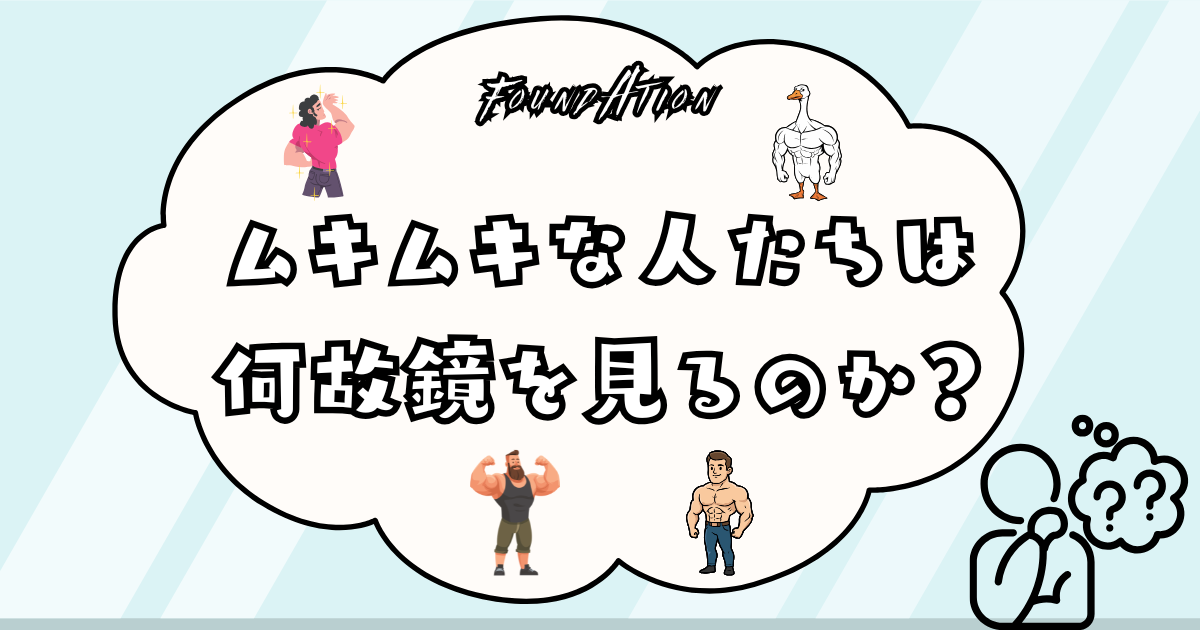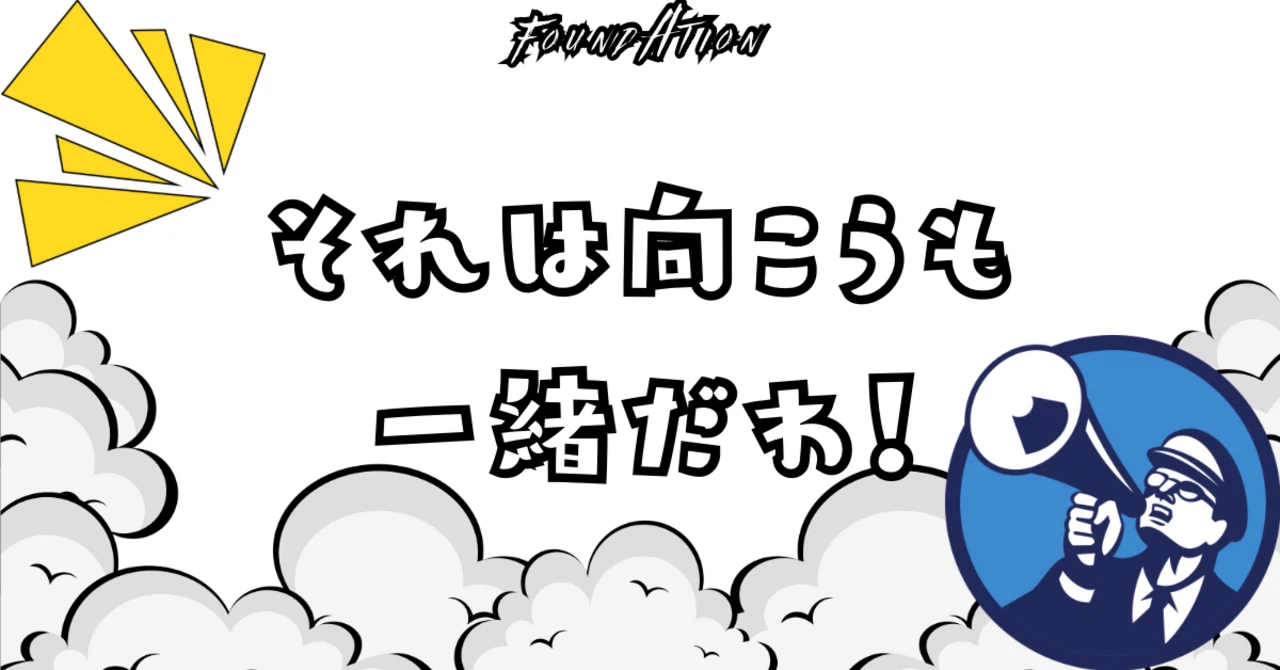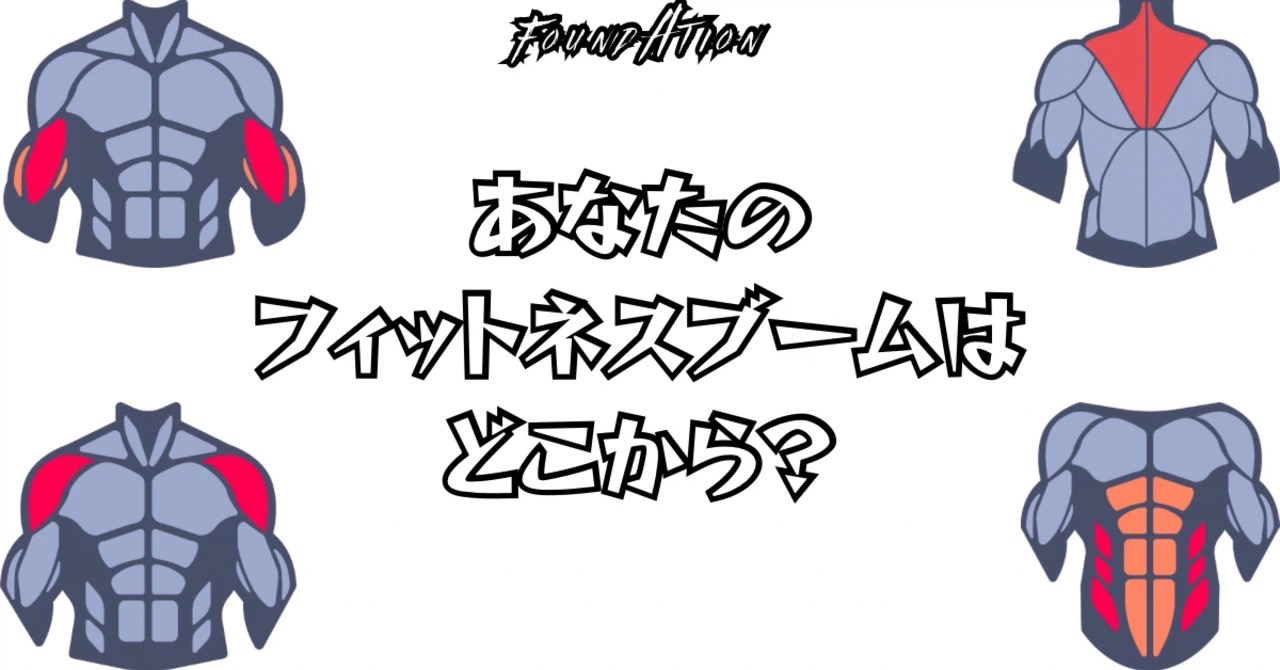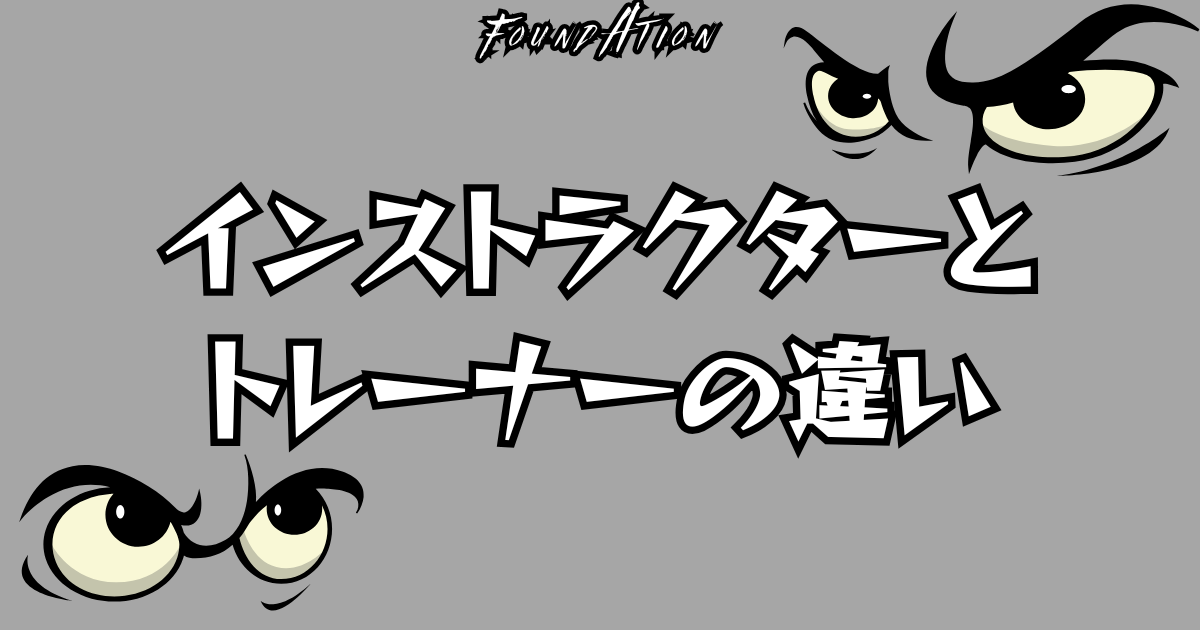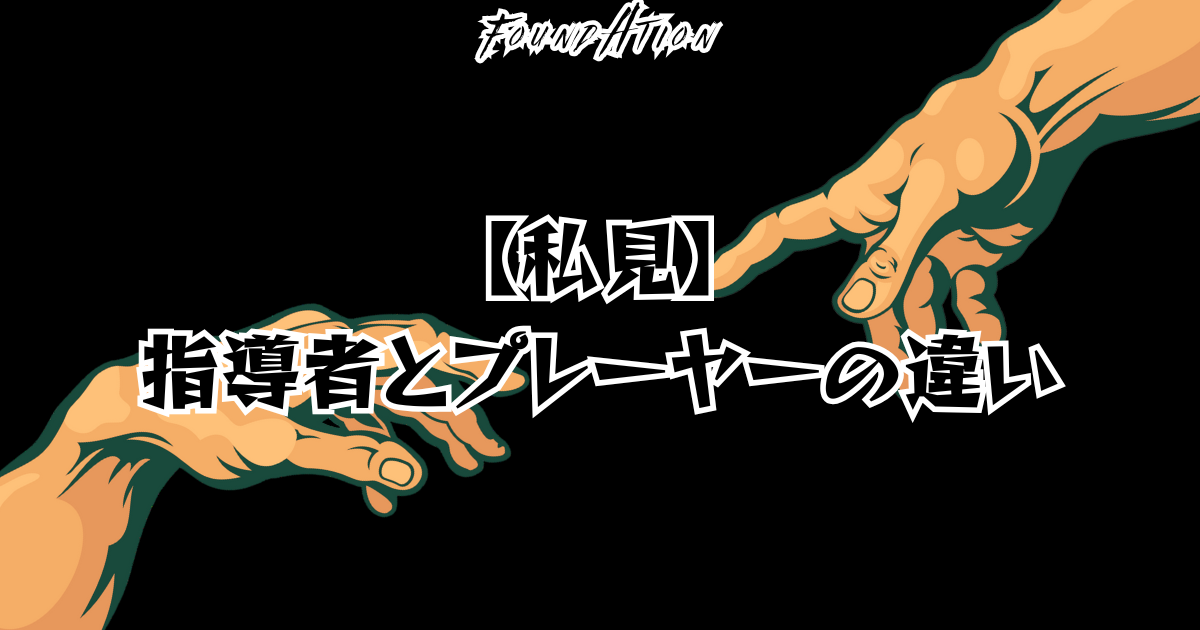クンダリーニヨガを嗜むようになってから、この独特な世界観を落とし込むのが中々大変だなと感じながら、日々の自主トレに励んでおります。
スッと理解出来ることばかりではないものが多いため、まだまだ言語化が難しい部分も多く、落とし込みに集中しております。
こういった
『分からない』
という感覚は、あまり良くないかのように言われることが多いですが、果たして本当にそうなのでしょうか?
この感覚の捉え方次第で、自身の世界観が広がっていくかもしれません。
今回はそんな、分からないという感覚について、私なりのトレーナーの視点を交えて確認していきましょう。
分からない=悪?

クンダリーニヨガに限らず、ヨガの世界観というのは非常に独特な上、ワイドで底が知れません。
その全てを理解することは、生きてる内に叶うかどうかも分からないぐらいのものだと思います。
現在も日々学ぶ中で分からないことの方が多いのですが
『ヨガはこの分からないというのも味わいのひとつなのだ』
ということを、とある方に教えていただきました。
そのお方とは、アシュタンガーヨガの指導者で、ヨガの先輩でもあります
『達田 有さん』
です。
達田さんのブログは詩的で美しく読みやすいだけでなく、読むだけでヨガとの付き合い方を知ることが出来るという素晴らしい内容となっておりますので、ヨガの深い世界観を知りたい方もそうでない方も、是非ご覧ください。
ヨガ指導者歴10年以上、且つ、現在もコンスタントに自主鍛錬を重ねているという、尊敬すべき大先輩です。
そんな達田さんに、ヨガとの付き合い方について、目から鱗な言葉を授けていただいたのです。
分からないという選択肢

その言葉とは
【分からないと言っても良いのがヨガ】
というものです。
私自身、達田さんからこの言葉を聞いて、指導者として指導の幅を広げる確信が持てました。
達田さんの言葉を裏付けるように、ヨガに関する書籍をいくつか読んでみると更にハッキリと見えてきます。
それは、以下のようなことが書かれているからです。
指導者だからといって上に立つのではなく、ほんの少しだけ前にいて手を差し伸べなさい。
私もまだまだ知らないことだらけだけれども、ほんの少しだけ知っているというだけだから、共に学んでいきましょう。
この慈愛に満ちた考えを持つというのが、東洋らしいヨガのスタンスだということですね。
分からないというのは決して悪いことではありません。
分からないから指導者をしてはダメなのではなく、分からない事が自分は多いと認識して、学びを止めない姿勢でいる事が指導者として大事なのだ
という風に、私は解釈しております。
トレーナー的には?

トレーナーの観点から見ると、分からないというのは悪?と言いますか良くないことだという印象があります。
それは何故かと言うと、科学的に実証されていることが多いからだというところにあると思います。
もちろん現状で説明が付くものを答えられないというのは、ただ単に勉強不足なだけということもありますが、そもそもの話、全部が全部分かる訳ではありません。
分からないことがあって当たり前です。
分からないことがあるのは、まだまだ伸び代がある証拠にもなりますので、むしろ喜ぶべきことじゃないでしょうか。
分からないというのは恥ずかしく思ってしまうものですが、よく考えてみてください。
人体は小宇宙と比喩されるぐらい、まだまだ未知の部分が大きいと言われておりますから、分からないことがたくさんあって当然です。
そんな人体ですから、今ある情報が変わらず常に同じということはほとんど有り得ないと思われます。
今日まで正しいとされていた情報が、明日には訂正されている可能性だってあるのです。
人体の情報が完成されて不変なものであるならば、専門書が今だに更新され続けるのはおかしいです。
このように、既に判明している情報ですら不変ではないのですから、保ち続ける姿勢はひとつです。
【学ぶことを止めない】
その姿勢を崩さなければ大丈夫です。
学ぶということは、分からないことを分かろうとする姿勢です。
ですから
分からないことは恥ずかしいのではなく、分からないことをそのままにしておくのが恥ずかしいのです。
私の場合
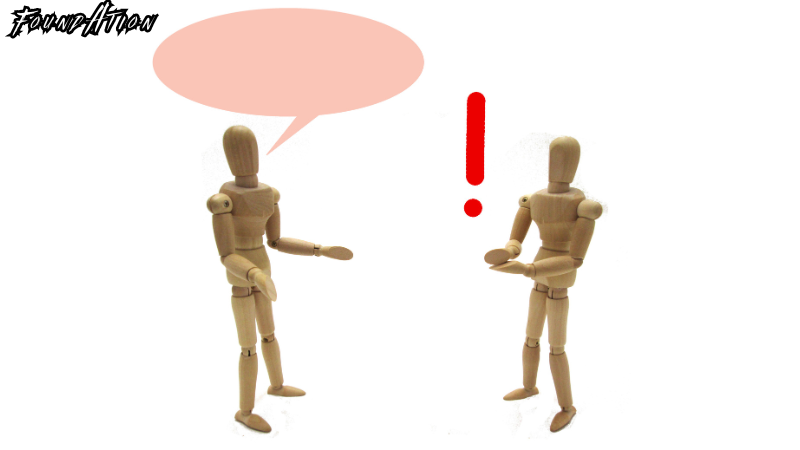
私自身、指導者として、この独特で掴みどころのない世界観を如何に自身に落とし込み、少しでも分かりやすく伝える為にはどうしたら良いかを考えていく時に、頼りになるのが今まで培ってきたトレーナーとしての知識です。
クンダリーニヨガは、自重で十分な負荷を肉体に掛けられるエクササイズが多く、トレーニングとしても優秀な為、私が培って来たコンディショニングテクニックの知識と非常に噛み合います。
最初、これは本当にヨガなのか?というのを疑うぐらいだったと言えば、少しは想像がつき易いでしょうか?
ただ、ヨガの概念上、より深く体の内側への意識を向けていく工程もあります。
そういった内部の感覚になると一気に理解が難しくなるので、途中で挫折しやすくなってしまうのですが、筋肉の反応や体感という分かりやすい部分に意識を向けるようにしていくことで、幾分分かりやすさが出て理解がしやすくなるのではないかと考えております。
始めて何も分からない状態で、いきなり
『今の動作は第何チャクラが〜』
と言われるよりかは
『今の動作はここを動かしてここの筋肉を刺激しましたよ〜』
の方が、リアルなので分かりやすいってことです。
それを積み重ねていった先に、更に一段も二段もディープな感覚を獲得出来るのだと思います。
そういったことを伝える時は特に、相手の理解度に合わせて順序を追った説明が大切ですね。
これが私なりの、分からないというのを分かりやすく伝えるために意識しているところです。
また理解の仕方のバリエーションとして
『インプットだけではなくアウトプットすることにより理解出来る』
というパターンもあります。
しょっちゅうあるのが説明している時です。
『なるほど!今の自分の説明は分かりやすい!よくこんな説明が出来たな!』
と自身で感心してしまうことがあります(笑)
ここだけ見るとアホのように聞こえますが(笑)冗談ではなく本当によくあるのです。
これは脳の素晴らしい働きだと思うのですが、インプットしたバラバラの知識が、アウトプットという作業に入った時に、関連項目で最適な答えになるように、瞬時に組み合わせてくれているのだと思います。
クンダリーニヨガを世に広めたヨギ・バジャン師曰く
『教えることでまた自身も学ぶ』
と云われ、積極的に指導を促していたみたいです。
私がよく体感する反応は、まさにその学びのひとつかと思われます。
教えることで理解が進めこともあるのが面白いですね。
おわりに

何でもそうですが、最初から全てが分かる訳ではありません。
積み重ねていく途中で分かることもあれば、分かったと思っていたら、また別な解釈が見つかったりしていくパターンもあると思います。
一筋縄でいかないからこそ、やりがいも出てくるというものです。
ですから、少しずつ焦らずに落とし込んでいけば、その理解度に合わせて言語化出来ることも増えてきます。
何でもかんでも説明出来てしまうなら、それはもう神様じゃないでしょうか。
なので、シンプルに諦めずにコツコツやるのみです。
【分かっていく過程が楽しくもあり、分からないというもどかしさもまた味わいである】
というのが、今、私がヨガを通じて学んで、改めてトレーナーとしても認識しているところです。
 宇都宮
宇都宮今回もご覧いただきありがとうございました!



パーソナルトレーニングについてのお問い合わせは
こちらからよろしくお願い致します!
本物のクンダリーニヨガに興味を持った方にオススメの書籍
・小沢隆,辻良史 ヨガ×武道 株式会社BABジャパン 2016
・辻良史 最強のメンタル ダイヤモンド社 2018

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/337d197e.ddd71c9f.337d197f.0a83be69/?me_id=1213310&item_id=18068415&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9870%2F9784862209870.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/337d197e.ddd71c9f.337d197f.0a83be69/?me_id=1213310&item_id=18910651&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3791%2F9784478103791.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)