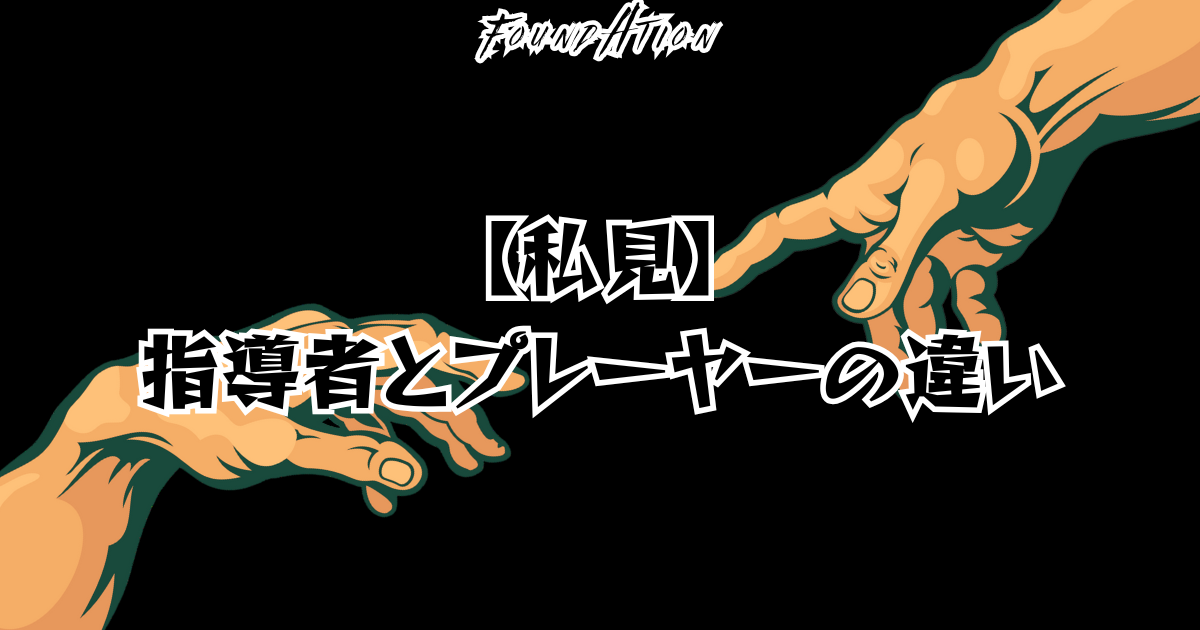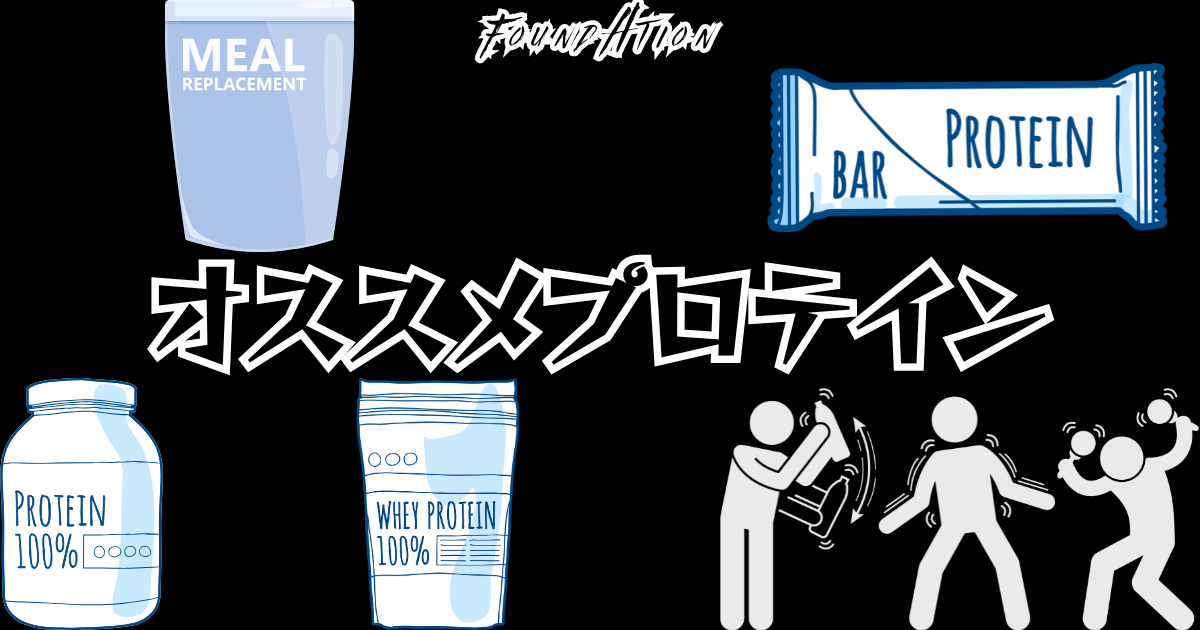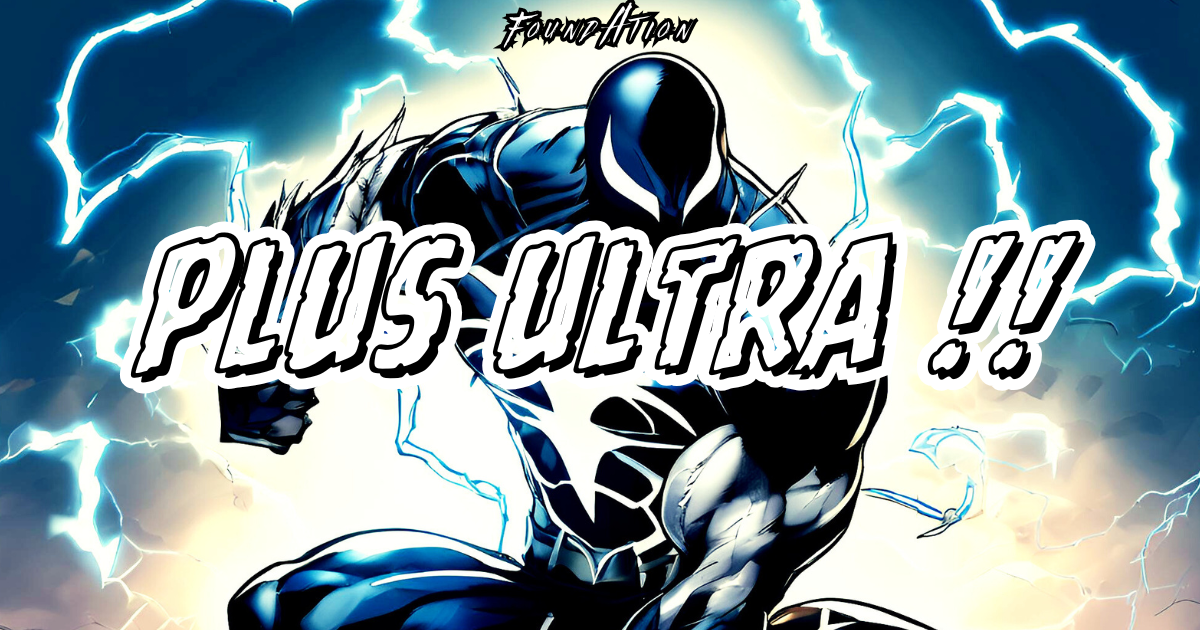以前の記事の最後に
『良いプレーヤーが良い指導者になるとは限らない』
と書いたのですが、今回はこの辺りを深掘りしていきたいと思います。
全くの別物
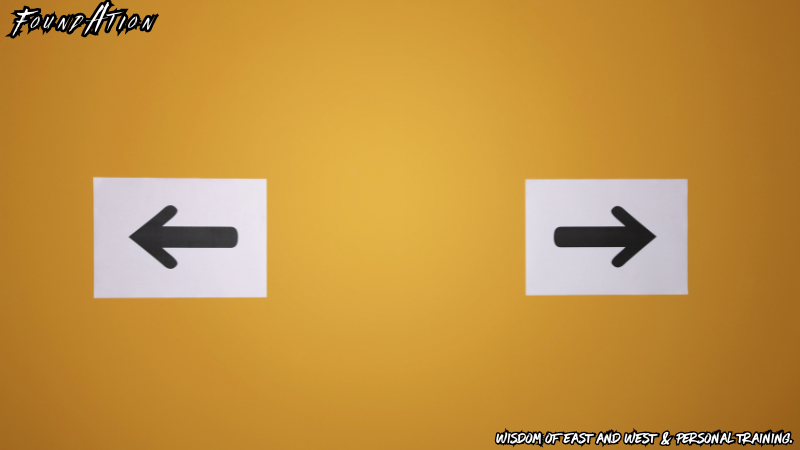
スポーツ業界において、プレーヤーが現役生活を終えて、指導者に転身するのはよく聞く流れだと思います。
一見するとその道のプロなので、指導者に回ったとしてもそれは何ら問題の無いように思えます。
しかし、そこに落とし穴があるのでは?と私は考えております。
その落とし穴とは
『指導者のスキルがあるかどうかはまた別の話』
ということです。
そもそもの話
【指導者】と【プレイヤー】は別物
なのです。
今までの私の経験上、ここの理解が出来ていない方が多いのでは?と感じております。
何故良いプレーヤーが良い指導者にシフトするのが難しいのでしょうか?
私見がたっぷり含まれていますが、私が思う違いについて述べさせていただきます。
スタンスによる違い
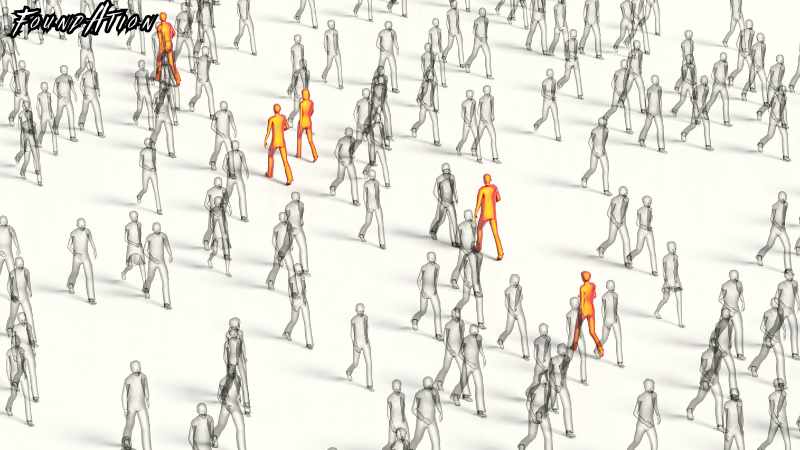
私自身、パーソナルトレーナーという仕事をしているので、他の方々の指導をたくさん拝見する機会があるのですが、指導という視点から見た時に感じる違いというのがあります。
それは、根本的なスタンスから来る違いなのでは?と考えております。
その違いとは、指導者なのか?プレーヤーなのか?ということです。
まずは、私が思う指導者とプレーヤーで感じる違いからご説明します。
違いは次の通りです。
指導者
↓
・理論を把握して言語化し、それぞれに合ったメニューの選択が出来て、且つ、伝わるように説明が出来るスキルが備わっている。
・そして理解はしているが、言語化出来ないものに関しては、出来る限り伝わりやすいような説明を考えることが出来る。
プレーヤー
↓
・感覚的に優れている方が多く、それ故説明も感覚的になりやすいので、言語化する際も感覚的なニュアンスになってしまうので伝わりにくい。
・例えば、速く走る為にはパーンッと走る!みたいに、自分が感じている感覚が他者にも同じように感じられるはずだと考えてしまう。
このように分けて考えてみると、その違いは歴然です。
元々、指導者としての頭があった上で活動している方は、他者の立場に立って考えることが出来るので、理解していただくまでに時間が掛かるということが分かった上での指導が出来ます。
指導する際にプレーヤーとしてのスタンスが抜け切ってない方は、自分中心に考えてしまうので、分かって当たり前という意識のまま指導してしまいます。
ですから
”他者が分からないことが分からない”
ため、伝わりにくくなってしまうのです。
このように比べてみると、こういった違いが出るのは当たり前のことです。
指導者とプレーヤーでは視点が変わるため、その役割の視点にシフトしなければなりません。
立場が変われば視点が変わるのは当然のことですから、勉強方法はもちろんスタンスも大きく変わるため、プレーヤーのままでは指導者になれないのです。
怪我が増えた理由

とは言いましたが、スポーツ業界ですと指導の対象者はアスリートになるので、スタンスを変えなくても指導者として、ある程度は活動出来ると思います。
ですが、フィットネス業界となるとどうでしょうか?
対象者は殆どが一般の方のため、指導となるとかなりデリケートとなります。
プレーヤーのままでは活動が難しいのです。
ここからは指導者をトレーナーに置き換えて進めていきます。
昨今、我々の業界は大々的に『怪我人出し過ぎ』という旨の警告を受けております。
フィットネスブームが来る前までは、そんな大々的な警告を受けたことがなかったのですが、そうなってしまった背景にはどういったものが考えられるでしょうか?
プレーヤーのまま活動しているトレーナーが増えた証拠だと思います。
要するに、コンテストに出ているからトレーナー始めましたという方が増えたというものですね。
ここに怪我に繋がってしまう要因が潜んでいるのではないかと思います。
運動指導における理論が抜け落ちてしまっているため、自分がやっていることをそのまま指導に充ててしまうので、怪我に繋がりやすくなってしまうのではないでしょうか?
コンテストに出るためには、ハードなトレーニングが必要になります。
一歩間違えれば即怪我に繋がるような、危険な内容のトレーニングです。
そんなハードなトレーニングを、初心者である一般のお客様にそのまま提供するなんて、危険以外の何ものでもありません。
怪我に繋がるのは目に見えております。
体を良くしたくて来ているのに、怪我をさせてしまっては元も子もありません。
そして大体の方は、そんなハードなトレーニングなんて求めておりませんし、必要ありません。
自分とお客様は当たり前ですが別人です。
「自分もこれをやってきたんだから、同じようにやるべきだ!」
という考えは、横暴以外の何者でもありません。
ナンセンスです。
トレーナーとは、お客様から求められて初めて活動が出来るのだということを意識しなければなりません。
トレーナーとしての資格を持ち、気を付けて活動しているトレーナーでも、怪我をさせてしまう危険性があるのがトレーニング指導です。
トレーニング指導は、それだけデリケートだということです。
偉そうに書いてきましたが、もちろん私自身完璧じゃありませんし、失敗もたくさんします。
レッスンの前はいまだに毎回緊張しますし、頭を悩ませながら行っております。
側から見ていて簡単そうに見えていたとしても、指導するというのは簡単なことではないのです。
おわりに

トレーナーの資格は国家資格ではありません。
トレーナーをやりたいとなった時に資格が必要ではないため、誰もがトレーナーを名乗ることが出来てしまうのです。
だからこそ、トレーナーを名乗るのであれば、資格を持つことが大事なのです。
資格を持っているということは、運動指導しても良いという最低ラインを学べているということが、第三者から保証されているという証になるのです。
それは、プレーヤーから指導者(トレーナー)になれた証です。
指導者(トレーナー)になりたい方は、何かひとつで良いので、定期的に協会誌や情報を発行・発信していたり、セミナーを定期的に開催している協会の資格を取得しておくと良いでしょう。
それはお客様からの信用にも繋がりますし、自分の自信にもなるので、指導者(トレーナー)としての責任感も持てます。
私が思う指導者(トレーナー)とは、縁の下の力持ちとして相手を支えて高めて、より良い位置にいけるようにそっと背中を押してあげる存在だと思っております。
今回の記事が、既に指導者(トレーナー)だったり、目指している方々の参考になれば幸いです。
 宇都宮
宇都宮今回もご覧いただきありがとうございました!



パーソナルトレーニングのお問い合わせは
こちらからよろしくお願いいたします!